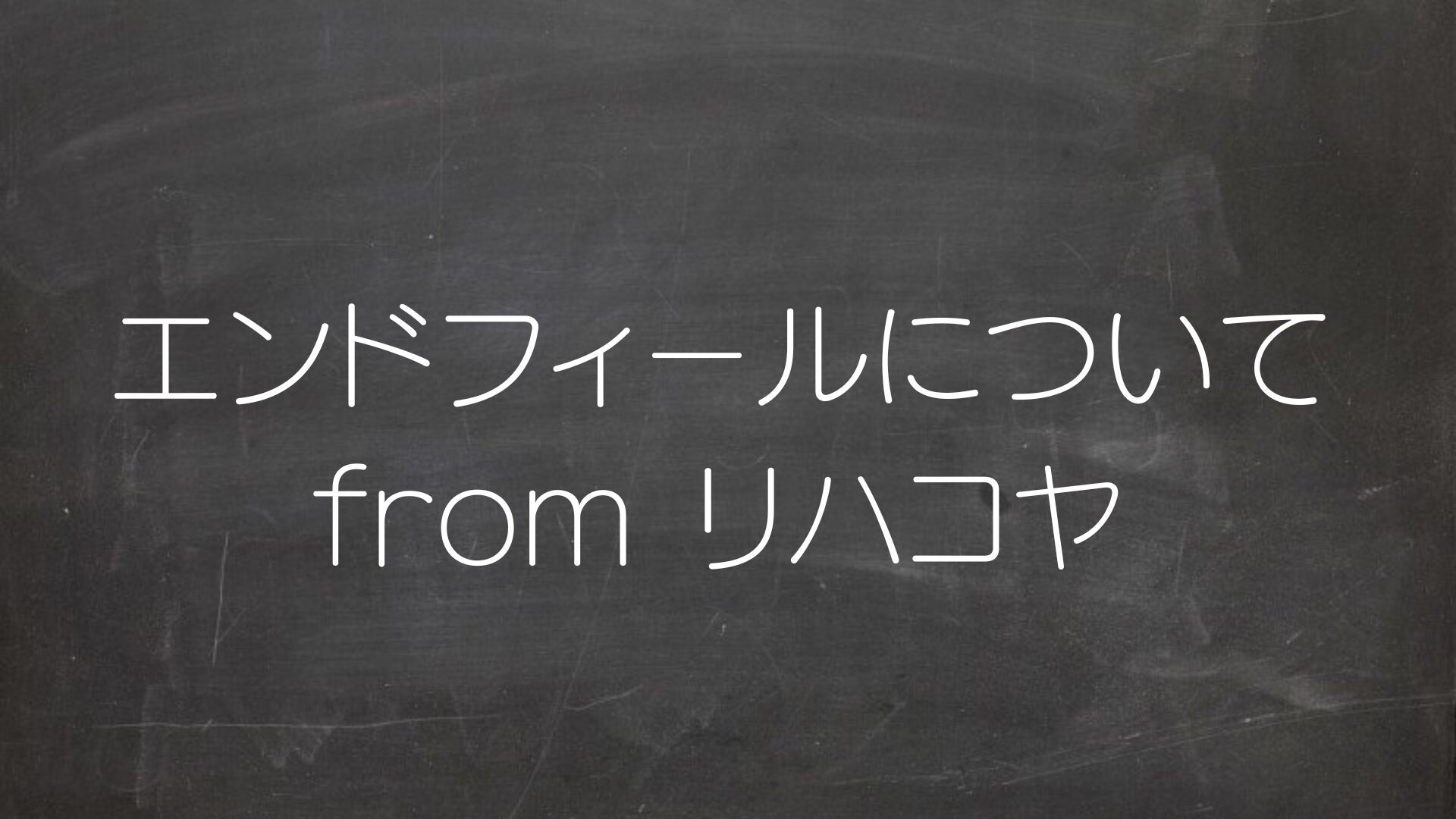毎週月曜日は一年前にリハコヤでライブ配信されたものの一部を文章でお届けします。
前回はROM測定時にエンドフィールを感じることで大まかな可動域制限の検討をつけることができるとお伝えしました。
前回の記事はこちら↓
今回はエンドフィールを感じる練習を続けていくと、どのように臨床に活かしていけるかについてお伝えしていきたいと思います。
股関節の運動方向とその制限因子について

上図は筋骨格系のキネシオロジーに記載されているもので、これは股関節の運動方向の制限因子を表にしたものです。
例えば、膝関節伸展位で股関節屈曲をした際に、参考可動域の80°以下で筋性のエンドフィールを感じた場合、ハムストリングスや薄筋による制限因子を疑います。
ハムストリングスと薄筋を区別するには、MMTを検査してみましょう。ハムストリングスのMMTが低下していれば、不全を起こしている可能性があります。また、薄筋は股関節外転時に最初に張ってくる筋なので、股関節外転で薄筋の状態をみてみるもの良いでしょう。
また、膝関節屈曲位で股関節を屈曲した際に可動域制限があった場合、坐骨大腿靭帯の下部や下方関節包に支障をきたしている可能性があります。ROM測定をする際にしっかりとエンドフィールを感じてみてください。アプローチをする部位が絞れてくると思います。
次に、膝関節伸展位で股関節を伸展した際に参考可動域以下で可動域制限があった場合、腸骨大腿靭帯と前方関節包と腸腰筋が疑われます。その場合、まずはトーマステストを実施します。トーマステストが陽性ならば腸腰筋を、陰性ならば靭帯・関節包が疑われるので、再度エンドフィールを感じるためにROM 測定を行います。
このように、エンドフィールを感じるだけでわかることはたくさんあります。
ROM測定でエンドフィールを感じることで、その後触診をするのか、整形外科テストを行うのか、MMTをとるのか、やることが変わってくると思います。是非臨床の参考にしてみてください。
まとめ
エンドフィールについて
1. ROM測定時にエンドフィールを感じることで大まかな可動域制限の検討をつけることができる。
2. エンドフィールは制限因子を特定するための大きなヒントとなる。
3. エンドフィールを感じることで、次に何の評価を行えば良いのかがわかる。
オンラインコミュニティ『リハコヤ』では、毎週2回こう言った内容をライブ配信しています。興味がある方はぜひお越しください。
↓ ↓ ↓
リハビリで悩む療法士のためのオンラインコミュニティ「リハコヤ」