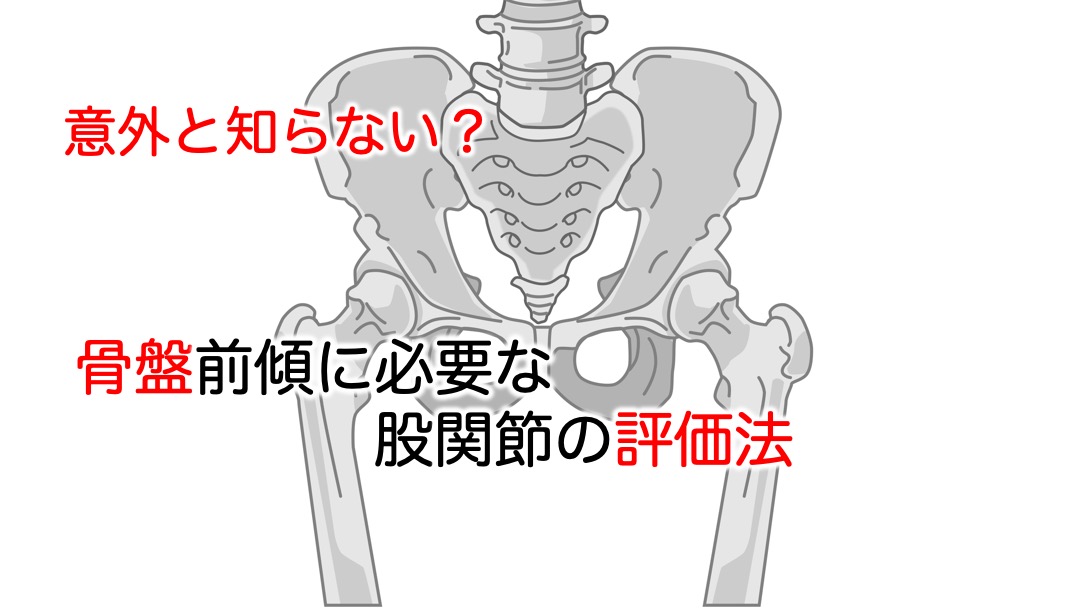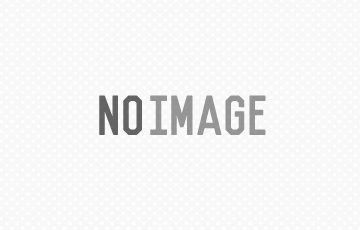こんにちは!
患者さん・利用者さんの問題点を一緒にさがす!を基本にしている加藤です。

今回は座位時に骨盤前傾に必要な股関節の評価をご紹介します!
目次
意外と知らない骨盤前傾に必要な関節
股関節
・参考可動域
・解剖学的可動域
・評価方法
終わりに
意外と知らない骨盤前傾に必要な関節
臨床ではよく座位での骨盤前傾を促していると思います。
では、骨盤前傾に必要な関節を確認してきましょう!
・股関節
・仙腸関節
・第4−5腰椎椎間関節
・第5腰椎―第1仙椎椎間関節
座位での骨盤の前傾には股関節の屈曲要素以外にも色々な関節が働いていることを念頭に入れておきましょう!
今回は股関節に注目していきます。
股関節
・参考可動域
座位での骨盤前傾に必要な股関節の動きは屈曲ですね。
では基礎運動学で股関節の参考可動域は何度になっているのでしょう?
答えは120度です。
でも、そのくらい角度があったら、他の関節の動き必要ないじゃん・・・と考えてしまいますね。次はもう少し解剖学的に考えていきましょう!
・解剖学的可動域
参考可動域の125度は実は、仙腸関節・腰椎の後弯・対側股関節の伸展が含まれて完成されます。
では本来の股関節の可動域はどのくらいでしょう?
解剖での骨盤と大腿骨との間の関節を計測した報告によると、股関節屈曲時に置ける骨盤と大腿骨との間の角度は93度と報告されています。
つまり、純粋な股関節のみの屈曲可動域は90度程度となっています。
つまり、骨盤前傾ができないのが、股関節の可動域なのか?他の問題なのか?はこの90度がポイントとなりそうですね!
(参考文献:関節可動域制限第2版 病態の理解と治療の考え方)
・評価方法
ではどうすれば骨盤前傾ができない要因が股関節なのか?その他なのか?を判断すればいいのでしょう?
答えはエンドフィールです。
股関節屈曲をしていくと、最初に結合組織由来のエンドフィールが90度前後であるはずです。
それよりも早くエンドフィールを感じてしまっていたら、その股関節は可動域が低下していると考えられます。
エンドフィールを意識して評価してきましょう!
終わりに
どうだったでしょうか?
骨盤前傾の条件とエンドフィールがポイントとなりますね!
ぜひ臨床でこの条件を意識して取り組まれてみてください。
また、今回ご紹介して評価法を学べる場をご用意しております。
療法士活性化委員会では、この評価・解釈を学べる場を用意しております。
Assessmentコースでは骨盤、脊柱、股関節、膝関節、足部、肩関節、呼吸・嚥下の評価・解釈・介入方法をお伝えしております。
この流れで受講していただくことで全身を短時間で評価することが可能となります。
1度学びにきませんか?
最後まで読んでいただきありがとうございます。
あなたも
当たり前のことが当たり前にできるようになり
一緒に信頼される療法士になりませんか?
療法士活性化委員会
認定講師
作業療法士 加藤 淳