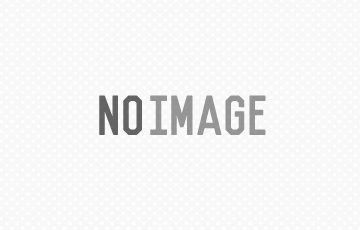皆さんこんにちは!作業療法士の内山です。
コロナ禍を経験し、感染症対策は日常業務の一部となりましたね。しかし、「感染対策を徹底すると、リハビリ内容が制限されてしまう…」と悩んでいませんか?
この記事では、多くのデイサービスが直面する「感染症対策」と「質の高いリハビリ」の両立という課題について、私が現場で実践し、利用者数のV字回復にも繋がった具体的な方法を成功事例を交えながら詳しく解説します。
- なぜ感染対策とリハビリの両立が重要なのか?
- 明日から真似できる具体的な感染対策とリハビリの工夫
- リアルな成功事例から学ぶアプローチのヒント
- スムーズな連携を生み出すスタッフ体制の作り方
なぜ?感染症対策とリハビリ両立の重要性
感染症対策とリハビリテーションの両立は、デイサービスにおいて避けて通れない最重要課題です。特にコロナ禍以降、利用者さんの安全を確保しながら、いかに身体機能や認知機能を維持・向上させるかが問われるようになりました。
注意すべきジレンマ
感染対策を重視しすぎて活動が制限されると、利用者さんのADLや認知機能の低下を招く恐れがあります。一方で、リハビリを優先して感染対策が疎かになると、利用者さんやご家族の信頼を失い、通所控えに繋がるケースも少なくありません。
事実、私のデイサービスでもコロナ禍初期に利用者数が一時的に半減しましたが、徹底した感染対策とリハビリの質向上を両立させることで、3ヶ月後には従来の8割程度まで回復しました。この経験から、両立こそが利用者さんの安心と機能維持の鍵だと確信しています。
具体的な感染対策とリハビリの工夫【環境設定から活動内容まで】
それでは、具体的にどのような工夫をしているのか、「環境設定」と「活動内容」の2つの側面からご紹介します。
① 環境設定の工夫:安全な空間作り
- ゾーニング方式の導入
施設内を「清潔ゾーン」「準清潔ゾーン」「汚染リスクゾーン」に明確に区分け。それぞれのエリアで活動内容と感染対策レベルを定義しました。
例:清潔ゾーン→個別機能訓練、準清潔ゾーン→少人数での作業活動、汚染リスクゾーン→手洗い場・更衣室 - レイアウトの見直しと換気の徹底
利用者さん同士の距離を2メートル以上確保できるよう、集団活動スペースを個別活動エリアに再編。さらに、30分ごとの換気タイムを設け、その時間を水分補給や休憩に充てています。
② 活動内容の工夫:リハビリの質を落とさないアイデア
- 感染対策をリハビリに組み込む
「手指消毒のポンプを押す動作」を上肢機能訓練に、「マスクの着脱練習」を巧緻動作訓練に、というように、感染対策そのものをリハビリプログラムとして活用しています。 - 個別対応の質的向上
集団活動が減った分、一人ひとりと深く向き合う時間が増加。これにより、利用者さんの細かな体調変化や在宅での困り事をより詳細に把握でき、的確なアプローチに繋がっています。
【実例紹介】感染対策下でのリハビリ成功事例3選
実際の事例を見てみましょう。少しの工夫で大きな成果に繋がったケースです。
- 状況:右手の機能低下があり、従来の集団体操では十分な訓練ができていなかった。
- 対応:毎回の手指消毒時に右手でポンプを押すよう意識づけ、個別指導を実施。
- 結果:日常生活に直結した機能訓練を自然な形で継続でき、右手の使用頻度が向上した。
- 状況:外出自粛で通所できず、認知機能の低下が心配された。
- 対応:ご家族の協力のもと、タブレットを使用したオンライン個別指導へ切り替え。自宅での体操や脳トレを継続。
- 結果:通所再開時も認知機能の大きな低下は見られず、むしろIT機器への興味関心が向上した。
- 状況:久しぶりの来所で歩行が不安定になり、更衣にも介助が必要な状態に。
- 対応:感染対策を徹底した個別リハビリプログラムを丁寧に継続。
- 結果:2ヶ月後には以前の状態まで回復。「先生たちがこんなに気を遣ってくれるなら安心」と、通所継続への意欲が向上した。
連携がカギ!スタッフ間のチーム体制はどう構築する?
感染対策とリハビリの両立は、一人の努力だけでは成り立ちません。多職種間の密な連携体制が不可欠です。
① 感染対策責任者を中心としたチーム体制
看護師を感染対策責任者とし、機能訓練士、介護士、生活相談員が連携するチームを構築。毎朝のミーティングで前日の状況を振り返り、その日の活動内容と対策レベルを確認します。
② 看護師と機能訓練士の連携強化
利用者さんの体調変化を早期に察知するため、看護師のバイタルチェックと機能訓練士の個別アセスメント情報を常に共有。軽度の体調不良でも、すぐに個別対応に切り替えられる体制を整えています。
③ 徹底した情報共有と透明性の確保
毎日の対策状況を写真付きで記録し、連絡帳などを通じてご家族へ共有。透明性を高めることで、安心と信頼に繋げます。また、月1回の感染対策勉強会には利用者さんにも参加いただき、共に知識を深めています。
今後の展望と継続的な改善
感染対策とリハビリの両立は、一過性のものではなく、今後のデイサービス運営のスタンダードとして定着させるべきです。
- 個別対応技術のさらなる向上:感染対策下で培った個別対応スキルは、あらゆる利用者さんのニーズに応えるための財産です。
- 柔軟な発想力の維持:制約の中から新たな可能性を見出す力は、今後のサービス向上に不可欠です。
- 安心感の継続的な提供:利用者さんとご家族が心から安心して通える環境を維持し続けることが、私たちの使命です。
まとめ:質の高いサービスは「両立」から生まれる
最後に、本日のポイントをまとめます。
- 感染症対策とリハビリは対立するものではなく、高いレベルで両立させることで、より質の高いサービスが提供できる。
- ゾーニングや個別対応の工夫により、安全性を確保しながら効果的なリハビリは実施可能である。
- 多職種連携を密にし、継続的に改善を行うことで、利用者と家族から選ばれる事業所になることができる。
トイレ動作の分析・アプローチスキルをさらに深めたいPT・OTの方へ
臨床で最も頻繁に関わるADLの一つ、「トイレ動作」。その評価やアプローチ、本当に自信を持って行えていますか?
利用者さんの尊厳とQOLに直結するこの重要な動作について、動作分析の基本から具体的な介入戦略、環境調整、多職種連携のコツまでを体系的に学び、明日からの臨床を変えるセミナーがあります。
このセミナーでは、トイレ動作をフェーズごとに分解し、詳細な動作分析を行う方法、対象者の機能障害に応じた具体的なアプローチ法、効果的な環境設定の工夫、そして円滑な多職種連携を実現するための情報共有のポイントまで、臨床現場ですぐに活かせる実践的な知識と技術を凝縮してお伝えします。