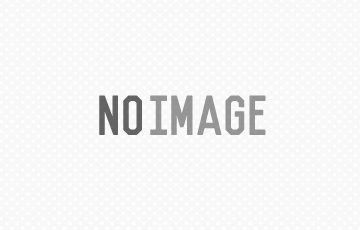こんにちは、理学療法士の大塚です。
前回のコラム(「病態が大事」の本当の意味)に続き、現場の療法士からこんな質問をよく受けます。
「臥位(寝た状態)で僧帽筋や多裂筋をあんなに時間をかけてリリースして、緩められるのに…。患者さんが坐位になった瞬間に、またカチカチに緊張が戻ってしまいます。
なぜ治療効果が持続しないんでしょうか? どうすれば座位まで効果を波及できますか?」
これは、多くの療法士がぶつかる「壁」だと思います。 非常に悔しい瞬間ですよね。
しかし、これはあなたの技術が低いからではありません。 もしかすると、私たちが無意識に持っている「治療のゴール設定」そのものが、ズレているのかもしれません。
1. 根本的な誤解:「緊張を落とすのが正義」なのか?
私たちは、患者さんの体が硬いと、つい「これを全部緩めなければ!」と思いがちです。 まるで「緊張 = 悪」「リラックス = 正義」かのように。
ですが、本当にそうでしょうか?
臥位(寝た状態)と座位(座った状態)では、体に求められる「仕事」が根本的に違います。
臥位(リラックスが目的)
- ベッドが全身を支えてくれる、重力から解放された状態。
- この時、姿勢を支える筋肉(抗重力筋)は休んでOKです。ここで緊張が残っているのは「異常」なので、リリース(緩める)のは正しいです。
座位(安定が目的)
- 坐骨で全身を支え、重力に真っ向から抗う状態(抗重力)。
- この時、重力で体が潰れないように、僧帽筋や多裂筋などの抗重力筋は「適切に」緊張する(=働く)必要があります。
つまり、「臥位で緩んだのに、坐位で緊張が戻った」のは、治療の失敗ではありません。
それは「重力に抗するという仕事が始まったので、筋肉が仕事に戻った」という、極めて正常な生理反応です。
2. 「レベル1」の治療の裏に「レベル2」の問題が隠れている
ここで、前回の「病態」の2つのレベルを思い出してみましょう。
- レベル1:局所の病態(状態)
- 「僧帽筋がカチカチに緊張している」という状態(症状)です。
- これに対し、私たちは「リリース手技」というレベル1の治療(対症療法)を行います。
- レベル2:全体の病態生理(メカニズム)
- 「なぜ、この患者は座るために、僧帽筋をカチカチに緊張“させなければ”ならないのか?」
- これが「根本的な原因(メカニズム)」です。
臥位で緩めても座位で緊張が戻る時、それは隠れていた「レベル2の問題(根本原因)」が「レベル1の治療(対症療法)」の結果、表に見えてきたということです。
3. なぜ、その患者は「過剰な緊張」を選んでしまうのか?
では、その「レベル2の問題(根本原因)」とは何でしょうか?
多くの場合、それは「安定性の欠如」です。
患者さんの神経系(脳)は、体を安定させたいと思っています。
しかし、本来働くべき「インナーマッスル(例:深層多裂筋、腹横筋、骨盤底筋群)」が、何らかの理由でサボっている(=神経系のエラー)。
脳(神経系)の”パニック”
「ヤバい!インナーが働かないと、体が倒れてしまう!」
「仕方ない!アウターマッスル(僧帽筋や脊柱起立筋)よ、お前たちが代わりにガチガチに固めて、なんとか体を支えろ!」
これが、「過剰な緊張」の正体です。
その緊張は、体が倒れないように必死で頑張っている「代償的な緊張(つっぱり棒)」なのです。
4. 私たちが本当にすべきこと:「リリース」から「再教育」へ
その「つっぱり棒(過剰な緊張)」を、臥位で一時的に取り除いても、坐位になって重力がかかった瞬間、脳は「危ない!」と感じて、全力で「つっぱり棒」を立て直します。
これが、緊張が戻るメカニズムです。
私たちが本当にすべきことは、「つっぱり棒(アウター筋)を緩める」ことではありません。
「正規の柱(インナー筋)を起こしてあげる」ことです。
臨床での治療ステップ提案
- レベル1の介入(準備): まず臥位でリリースします。これはOKです。 目的は「緊張をゼロにする」ことではなく、「過剰なアウターの”緊張を抑えて”、インナーが働きやすくする」ためです。
- レベル2の介入(本番): アウターの緊張が抑えられたら、インナーマッスル(深層多裂筋など)を働かせる運動(例:軽い骨盤後傾など)を行います。 「そうそう、この筋肉が君の柱だよ」と神経系に再教育します。
- レベル2の介入(統合): そのインナーのスイッチを入れたまま、ゆっくりと坐位になってもらいます。
インナー(正規の柱)が適切に働けば、脳は「あ、安定した。もう大丈夫だ」と安心します。
その結果、アウターマッスル(僧帽筋など)は「もう俺たちが過剰に頑張らなくていいね」と、自ら緊張を解いてくれます。
5. まとめ
「坐位になると緊張が戻る」のは、あなたの技術のせいではなく、患者さんの脳が「そうせざるを得ない」からです。
その緊張は「悪」ではなく、「安定性が足りないよ!」と教えてくれる重要なフィードバック(情報)です。
私たちのゴールは「緊張をゼロにする」ことではありません。
「その姿勢・その動作に必要な筋緊張を、適切で効率よく発揮できる」ように、神経系を再教育することです。
「リリース」の先にある「動きの再教育(モーターリコントロール)」。
そこまで含めて「病態生理(レベル2)」へのアプローチだと考えてみてください。
この記事では、「緊張」をフィードバックとして捉え、インナーの再教育に繋げる思考法を解説しました。
この「レベル2」のアプローチを行うには、まず『今インナーが働いているか?』『アウターが過剰に頑張っていないか?』を感じ分ける触診技術が不可欠です。
臥位でのリリース(レベル1)から、坐位での再教育(レベル2)まで。その土台となる「触る技術」を学びたい方は、こちらのセミナーをご覧ください。