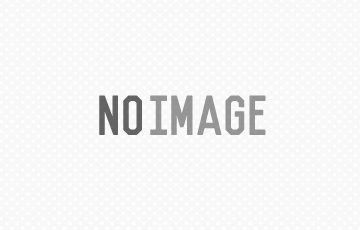みなさんこんにちは。作業療法士の仲田です。
今回は、ICFの環境因子に対しての作業療法をお伝えできればと思います。ICFを理解することで、より包括的な評価と効果的なアプローチが可能になります。
実際にZoomのナイトセミナー「OTしゃべり場」というADLなどを話し合う場で出てきたICFの環境因子に関する会話を一部お伝えしていきます。
ICFの環境因子って何を評価すればいいの?現場でよくある質問にお答えします
環境因子の3つの分類を理解しよう
ICF環境因子の3分類
- 物的環境:住宅構造、福祉用具、交通手段、建築物のバリアフリー化など
- 人的環境:家族、友人、医療従事者、介護者、職場の同僚など
- 社会制度的環境:法律、社会保障制度、介護保険、障害者雇用制度など
環境因子は促進にも阻害にもなる!?意外と知らない両面性
実践で使える!環境因子の効果的な記載方法
活動・参加との関連を明確にする記載のコツ
記載例の比較:Before → After
❌ Before(改善前)
・車いすを使用
・家族と同居
✅ After(改善後)
・段差が多いため、屋内移動時に転倒リスクがある
・家族の支援により通所リハへの参加が可能となっている
まとめ:ICF環境因子評価の3つのポイント
- 促進因子と阻害因子の両面を記載する
環境が対象者にとってプラスに働いているのか、マイナスに働いているのかを明確に区別して記載 - 活動・参加との関係性を具体的に示す
単なる情報の羅列ではなく、その環境が実際の生活にどう影響しているかを具体的に記述 - 客観的事実と本人や家族の主観も含める
物理的な環境だけでなく、心理的・文化的側面も含めた包括的な評価を心がける
いかがだったでしょうか。ICFの環境因子を正しく理解し、適切に評価・記載することで、より効果的な作業療法の実践につながります。視野が広がり少しでも役に立てたのなら幸いです。
「ICFを使った評価が難しい」「もっと実践的な記載方法を学びたい」
そんな想いを持つ療法士仲間と一緒に、臨床の質を高めませんか?
療法士活性化委員会では、ICFに基づいた目標設定やアプローチ法など、臨床の質を上げるためのオンライン講座を多数開催しています。