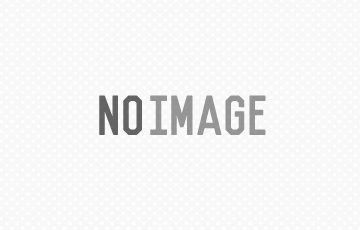「70mmHgの圧迫を2時間…」って、結局どういうこと?
褥瘡予防の研修で必ず聞くこの数字。分かっているつもりでも、いざ臨床で患者さんの身体に触れるとき、「この体位で本当に大丈夫かな?」「あと何分なら動かさなくてもいい?」と、具体的な判断に迷うことはありませんか?
褥瘡対策は、単なる体位交換のルーティンではありません。そこには、虚血、不動、そして環境という複雑に絡み合う「3つの要因」と、それを裏付ける科学的なメカニズムが隠れています。
このコラムでは、私たちが無意識に見過ごしがちな「褥瘡発生の本当のサイン」に光を当てます。当たり前の知識を深掘りすることで、「なるほど!だからこのポジショニングが必要なんだ!」という新しい気付きを一緒に見つけていきましょう。
この記事はこんな人にオススメです
- 褥瘡の基礎知識や発生メカニズムを臨床に活かしたい方
- 具体的な褥瘡予防の実践方法(ポジショニング)を知りたい方
- 褥瘡のリスク評価やケア計画の根拠を深めたい方
本日の疑問(この記事でわかること)
- Q: 褥瘡の発生要因は?
A: 「虚血」「不動」「環境(内的・外的)」の3点に注目して解説します。 - Q: 褥瘡の対策の考え方は?
A: 発生要因(虚血・不動・環境)にどうアプローチするかを整理します。 - Q: 褥瘡予防に有効なポジショニングは?
A: ガイドラインで推奨される「30度側臥位」と「90度側臥位」の使い分けを解説します。
褥瘡(じょくそう)とは?
日本褥瘡学会では、創傷の原因によって「自重関連褥瘡」と「医療関連機器褥瘡」を区別しています。
- 自重関連創傷(いわゆる褥瘡・床ずれ)
- 「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡となる」と定義されています。
- 医療関連機器褥瘡
- 「医療関連機器による圧迫で生じる皮膚ないし下床の組織損傷であり、厳密には従来の褥瘡すなわち自重関連褥瘡と区別されるが、ともに圧迫創傷であり広い意味では褥瘡の範疇に属する。(中略)粘膜に発生する創傷は含めない」と定義されています。
「一定の持続時間」とは? 70mmHgと2時間の根拠
1959年のKosiakの研究(Etiology and pathology of ischemic ulcers)で、イヌやラットの組織に外部から様々な圧力と時間を加える実験が行われました。この結果、70mmHgの圧迫を2~3時間行ったことで不可逆的な組織変化(壊死)が起こり始めることが示されました。そのため、一般的に「70mmHgの外圧が2時間以上持続すると褥瘡が発生しやすい」とされています。
しかし、毛細血管がつぶれる圧は32mmHgといわれており、70mmHgより低い圧でも褥瘡が発生する可能性があり注意が必要です。一方で褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)にて、適切な体圧分散マットレスを使用している場合には4時間以内での体位交換でも良いとされています。
【セラピストのための豆知識】
余談になりますが、毛細血管再充満時間(末梢循環の状態評価)の測定時に、爪下の皮膚を白く(虚血状態に)させるのに必要な圧力は、100mmHg〜200mmHg程度といわれています。これを踏まえると、訓練場面や活動・参加場面では、いかに容易に70mmHgを超えやすいかがイメージできるのではないでしょうか。
褥瘡の「3大発生要因」とは?
褥瘡の発生要因として、①虚血要因、②不動要因、③環境要因(内的・外的)の3つで考えると理解しやすいです。
1. 虚血要因
32mmHg(毛細血管をつぶす圧)~70mmHg(組織変化が起こる圧)以上の外圧が持続すること。
2. 不動要因
虚血を引き起こす外力を一定時間持続させること。目安として2時間以上で発生リスクが増大します(適切な体圧分散マットレス使用時は4時間以上)。
3. 環境要因(内的要因)
患者さん自身の身体的な要因です。
- 骨突出
皮下脂肪層が薄い(るいそう等)と、圧迫が加わりやすくなります。 - 関節拘縮
股関節・膝関節の屈曲拘縮や股関節の開排制限は、臀部の体圧を高め、体動を困難にします。 - 栄養状態
低栄養は、組織の耐久性低下、褥瘡の悪化や治癒遅延に関与します。
など。
4. 環境要因(外的要因)
患者さんを取り巻く外的な要因です。
- オムツの使用(湿潤)
尿・便失禁により皮膚が浸軟(しんなん)すると、コラーゲン繊維が弱まり、皮膚の耐久性が低下します。 - ベッドや着衣のシワ
シーツや衣服のシワが局所的な圧迫を強める可能性があります。 - 不適切な体位交換
体位交換のやり方によって摩擦やずれが大きくなり、皮膚への負担を増やす可能性があります。
など。
褥瘡対策の考え方:3大要因へのアプローチ
褥瘡の発生要因(虚血・不動・環境)それぞれに対応していくことが基本です。
- 1. 虚血対策
- マットレスやクッションの選定、座位能力に応じた車いすの選定、除圧動作の指導など。
- 2. 不動対策
- 定期的な体位交換、複数の体位(背臥位・側臥位など)への体位交換、離床・活動・参加の促進など。
- 3. 環境対策(内的要因)
- 関節可動域訓練、筋力増強訓練、栄養状態の改善(栄養士との連携)など。
- 4. 環境対策(外的要因)
- 早期のトイレ動作の獲得、適切なベッドメイキングと更衣介助、適切な体位交換技術(摩擦・ずれの防止)の実施など。
褥瘡の好発部位
筋肉や脂肪組織が少ない「骨突出部」に多く発生します。
- 背臥位
後頭部、肩甲骨部、肘頭部、仙骨部、踵骨部 など - 側臥位
耳介部、肩峰突起部、腸骨部、大転子部、膝関節部、外果部 など - 座位
背部(特に円背の場合)、尾骨部、坐骨結節部 など

(参考:看護roo! イラスト集)
褥瘡予防に選択する体位は?(30度・90度側臥位)
褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)にて「30度側臥位、90度側臥位ともに行うよう勧められる」とされています。
30度側臥位
- 利点:
肩や殿部の接触面積を大きくして、骨突出部(大転子部・仙骨部・肩峰部など)の圧迫を軽減できます。 - 注意点:
「るい瘦が強く、仙骨突出が著明な場合」や「本人が安楽ではなく、自力で体位を変えてしまう場合」は注意が必要です。
90度側臥位
- 利点:
「臀部の支持組織が少ない場合」や「臀部(仙骨部・尾骨部)に既に褥瘡がある場合」に利用可能です。また「30度側臥位より安楽な場合」にも選択されます。 - 注意点:
30度側臥位に比べ、他の骨突出部(肩峰、大転子、外果など)への接触圧は高くなりやすいため、適切な圧分散や体位交換の時間により注意が必要です。
まとめ
褥瘡予防の鍵は、ルーティン作業ではなく、患者さん一人ひとりの状態を評価することにあります。今回のポイントを臨床判断に活かしてください。
- 褥瘡の発生メカニズムと要因は「虚血・不動・環境」にある
- 対策は発生要因へのアプローチであり、体圧分散と体位変換(ポジショニング)が基本
- 褥瘡予防に有効な体位として「30度側臥位」と「90度側臥位」が推奨されており、患者さんの状態に応じた使い分けが重要
参考文献・引用文献
- 褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)(Mindsガイドラインライブラリ)
- 日本褥瘡学会 用語集
- 楫西ミチコ:褥瘡ケアの基本、秀和システム、2020年
- 寺師浩人監修、杉本雅晴、日高正巳ら編集:褥瘡のリハビリテーション医療、照林社、2024年
» 関連記事:ポジショニングの基礎と臨床応用について詳しく見る