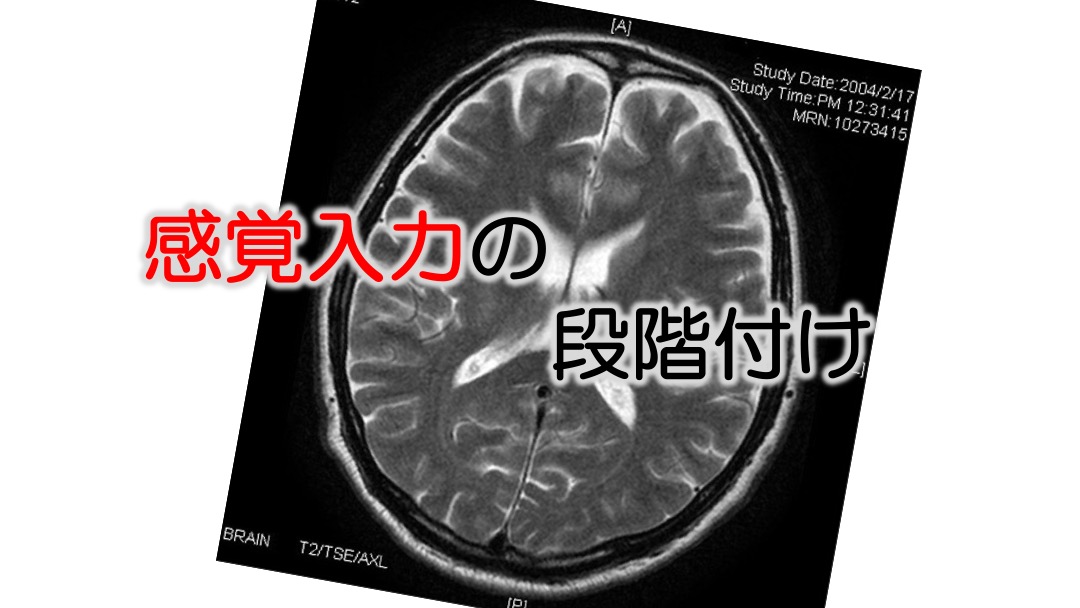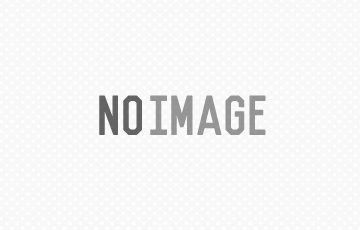こんにちは!
患者さん・利用者さんの問題点を一緒にさがす!を基本にしている加藤です。

脳卒中後のリハビリで多くの場面で遭遇する感覚入力。
感覚が鈍麻していることで
・危険因子の回避がしづらい
・協調性の低下
・筋力のコントロールの低下
などの要因の1部となってきますね。
では、脳卒中後のリハビリにおいて感覚を促通する際に、どうやっていけばいいのでしょう?脳卒中の回復段階に沿って考えていきましょう!
目次
感覚入力の順番
なぜ硬いものから?
感覚の回復段階
まとめ
感覚入力の順番
一般的に臨床では感覚入力の順番が大体決まっていますね。
- 硬く重いもの(木材など)
- 重くなく柔なくないもの(小豆など)
- 軽く柔らかいもの(スポンジなど)
という順番で感覚入力を促しているのではないでしょうか?
なぜ硬いものから?
では、なぜ硬いものから順にしているのでしょうか?
それは、硬く重いものを持つと使われている感覚受容器が変わってきます。
硬く重いものを持った際には深部感覚の受容器が主に働きます。
一方で軽く柔らかいものでは表在感覚と深部感覚がそれぞれ協調して働かないとうまく持てません。
つまり難易度で言っても硬く重いものの方が簡単なのです。さらに回復段階を考えても硬く重いものは導入にはとても良いものです。
感覚の回復段階
感覚の回復は
深部感覚が初めに回復し、その後表在感覚が回復していきます。
つまり、回復段階を考えると、まず深部感覚を促していくことが良いと考えられます。
その観点から考えても硬く重いものを導入に入れるのはとても良さそうですね。
まとめ
どうだったでしょう?
感覚の回復段階と難易度設定を考えると硬く重いものからの導入がとてもいいことが理解できますね。ぜひ、今のままの順番で感覚入力を続けてみてください。
この評価方法・分離促通方法をコースで学べます。
来年1月より開催される3ヶ月で学ぶ
脳血管疾患に対する評価とアプローチ〜麻痺の分離と促通法と動作の再獲得〜
DVDでも学べます。
麻痺の分離と促通法3枚組
最後まで読んでいただきありがとうございます。
あなたも
当たり前のことが当たり前にできるようになり
一緒に信頼される療法士になりませんか?
療法士活性化委員会 認定講師
お悩み相談室 代表
加藤淳
住所:東京都板橋区成増1−12−8 小出マンション202
電話番号:070-1395-8506
メールアドレス:nagomi5409@yahoo.co.jp
HP:https://ptotst-supporter.jimdofree.com
 この記事が「おもしろい!」「為になった!」と思ってくださった方は、ぜひ「シェア」や「いいね!」をお願いします!!
この記事が「おもしろい!」「為になった!」と思ってくださった方は、ぜひ「シェア」や「いいね!」をお願いします!!
今すぐ「いいね!」ボタンを押して「療法士のためのお役立ち情報」をチェック!
↓ ↓ ↓ ↓