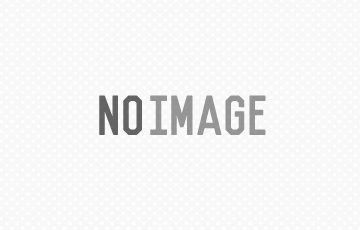疼痛について解説するシリーズの第24回目です。今回は、理学療法士・作業療法士が理解しておくべき疼痛治療における薬物療法について解説します。
疼痛治療において薬物療法は重要な手段の一つです。疼痛は、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、痛覚変調性疼痛に分類され、それぞれの病態に応じて薬剤が選択されます。リハビリテーション職にとっては、薬剤の基礎知識を理解し、薬物の作用時間や副作用に応じて運動療法を適切に調整する視点が求められます。
疼痛のタイプ別薬物療法
1. 侵害受容性疼痛:炎症や組織損傷に伴う痛み
炎症や組織損傷により末梢の侵害受容器(痛みセンサー)が刺激されることで発生します。このとき、細胞膜から放出されたアラキドン酸がシクロオキシゲナーゼ(COX)によって代謝され、プロスタグランジン(PG)が産生されます。PGは知覚神経の感受性を高め、痛みを強める要因となります。
NSAIDs(ロキソプロフェン、セレコキシブなど)
- 一般名・商品名
- ロキソプロフェン:ロキソニン
- セレコキシブ:セレコックス
- 作用機序
COXを阻害してPGの産生を抑制することで、疼痛や炎症を軽減します。
(COX-1:胃粘膜保護や血小板機能に関与(恒常型)、COX-2:炎症時に誘導され、PG産生を促進(誘導型)) - 臨床例
変形性関節症、打撲、捻挫、骨折後の急性期疼痛など - 副作用とリスク管理
胃腸障害、腎機能障害、心血管リスク(特に非選択的NSAIDs)。高齢者ではCOX-2選択的薬(例:セレコキシブ)や胃粘膜保護薬(PPIなど)との併用が推奨されます。
アセトアミノフェン(カロナール)
- 一般名・商品名
アセトアミノフェン:カロナール - 作用機序
中枢神経系でPG産生を抑制し、鎮痛・解熱効果を発揮します。抗炎症作用はほぼありませんが、消化器障害や腎障害のリスクが低いため、比較的安全です。
(作用機序:中枢におけるセロトニン作動性経路や内因性カンナビノイド系の関与が示唆されている) - 臨床例
軽度〜中等度の痛み(筋骨格系)、慢性関節症、術後疼痛など - 注意点
高用量時の肝障害に注意。総使用量(1日最大4000mg)を超えないよう、併用薬を含めた確認が必要です。
2. 神経障害性疼痛:神経の損傷や過敏により生じる痛み
神経の損傷・変性により、通常では感じない刺激に対しても痛みを生じる「異痛症」や「アロディニア」が現れるのが特徴です。
プレガバリン・ミロガバリン
- 一般名・商品名
- プレガバリン:リリカ
- ミロガバリン:タリージェ
- 作用機序
電位依存性Caチャネルのα2δサブユニットに結合し、グルタミン酸などの神経伝達物質の放出を抑制します。 - α2δサブユニットとは
電位依存性カルシウムチャネル(Voltage-Gated Calcium Channels, VGCCs)の補助サブユニット。主にチャネルの細胞膜への輸送を助けたり、チャネルの開閉特性に影響を与える補助的な役割を担っています。神経終末に存在し、Ca流入に伴って痛み信号の伝達物質(例:グルタミン酸)が放出されるのを助けます。ここをブロックすることで痛みの神経伝達を抑えることができるとされています。 - 臨床例
帯状疱疹後神経痛、糖尿病性末梢神経障害、術後慢性疼痛など - 副作用
眠気、めまい、浮腫(→転倒リスクに注意) - リハビリの視点
服薬時間と眠気のピークに合わせて運動負荷を調整。歩行訓練や起立動作時の安全管理が重要です。
SNRI(例:デュロキセチン)
- 一般名・商品名
デュロキセチン:サインバルタ - 作用機序
セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害することで、下行性疼痛抑制系を活性化し、痛みの伝達を抑えます。 - 再取り込み阻害によって何が起こるのか
通常、セロトニン(5-HT)やノルアドレナリン(NA)はシナプスに放出された後、神経終末に再取り込まれて再利用されます。SNRIはこの再取り込みを阻害することで、シナプス間隙におけるセロトニンとノルアドレナリンの濃度を高めます。これにより、脳幹から脊髄後角へ投射される下行性疼痛抑制経路が強化され、疼痛信号の伝達が抑制されます。特に、神経障害性疼痛や慢性疼痛においてこの下行性制御の低下が関与しているため、SNRIはその是正に有効とされています。 - 臨床例
慢性腰痛、線維筋痛症、変形性関節症の神経障害性成分を伴う痛みなど - 副作用
吐き気、不眠、血圧上昇など - リハビリの視点
服薬初期の離脱症状や日内変動(例:朝のだるさ)を把握し、運動時間の調整や生活指導に役立てます。
3. 痛覚変調性疼痛:中枢過敏による痛み
身体的な損傷と一致しない痛みや、広範な部位に痛みが広がる特徴があります。脊髄や脳での痛覚処理の過敏化(中枢感作)が関与します。
NMDA受容体拮抗薬(ケタミンなど)
- 一般名・商品名
ケタミン:ケタラール(静注薬) - 作用機序
グルタミン酸NMDA受容体を阻害し、中枢感作の抑制を図ります。wind-up現象(反復刺激による痛覚の増幅)を抑える働きがあります。 - NMDA受容体とは
NMDA受容体(N-メチル-D-アスパラート受容体)は中枢神経系に広く分布するグルタミン酸作動性の興奮性受容体の一種で、特に記憶・学習・中枢感作に関与しています。通常は静かに存在していますが、持続的な侵害刺激により活性化するとカルシウムイオンが細胞内へ流入し、神経細胞の興奮性を長期的に高める作用があります。中枢感作(central sensitization)やwind-up現象と呼ばれる過敏化機構の中核を担い、痛みが本来の刺激強度以上に知覚される状態を引き起こします。NMDA受容体を遮断することで、こうした異常な痛覚増強を抑えることができるため、難治性の慢性疼痛に対してNMDA受容体拮抗薬(例:ケタミンなど)が用いられることがあります。 - 適応例
CRPS、難治性慢性疼痛 - 副作用
幻覚、血圧上昇、意識混濁 - 注意点
日本では慢性疼痛に対してのケタミン使用は保険適応外(使用は入院管理下が多い)
トラマドール
- 一般名・商品名
トラマドール塩酸塩:トラムセット、トラマール - 作用機序
弱オピオイドとして、μオピオイド受容体への弱い親和性による鎮痛作用に加え、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用(SNRI様作用)を有する点が特徴で、神経障害性疼痛にも効果を示す場合がある。これらの作用により、非オピオイド薬で十分な効果が得られない場合に用いられることが多い。 - 臨床例
THA/TKA術後、骨折後疼痛、癌性疼痛の軽症時など - 副作用
吐き気、便秘、眠気、依存傾向(少ないが注意) - リハビリの視点
疼痛の混在(侵害受容性+神経障害性)に対して用いられるケースが多く、疼痛変化のモニタリングが重要。
眠気やふらつきによる転倒リスクや、神経障害性疼痛への使用背景などを把握しておくことが望ましい。
活動量が増えることで薬効評価が困難になることもあり、患者の主観と客観評価の両立が求められます。
リハビリテーション職が行うべき薬剤関連のリスク管理
- NSAIDs使用時:
疼痛緩和による過負荷に注意。一時的に動けても関節や筋の炎症が持続している可能性あり。 - Caチャネル作動薬やSNRI使用時:
ふらつき・眠気による転倒予防を徹底。初期訓練時は付き添い・安全確認が必須。 - オピオイド使用時:
意識変容や協調運動障害による転倒・ADL低下の評価が必要。 - 慢性疼痛患者:
薬剤のみに頼らず、身体活動・心理的介入を併用した包括的アプローチが重要。
まとめ:リハビリテーションにおける薬物療法の位置づけ
疼痛治療において薬物療法は症状の軽減手段であり、患者さんの目標(HOPE)達成に向けた支援の一部です。
- 薬剤の作用時間と副作用を考慮して運動内容・タイミングを調整
- 服薬による転倒や倦怠感などのリスクに対する環境調整
- 疼痛の病態理解と薬物への配慮を通じて、リハビリの介入精度と安全性を高めることが可能
さらに深く学びたい方、実践的なスキルを身につけたい方には、こちらのコースがおすすめです。
慢性疼痛に対する痛み・神経の科学的根拠をもとにした末梢神経への徒手介入法 〜DNM(Dermo Neuro Modulating)〜 BASICコース
このコースでは、神経系への徒手介入の基礎を学び、臨床での応用力を高めることができます。ぜひご検討ください。