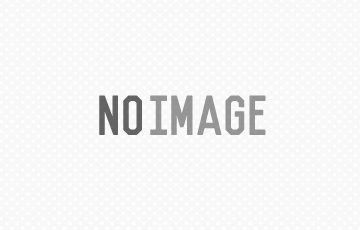こんにちは。理学療法士の赤羽です。
「痛みがなかなか治らない」「前より痛みが広がってきた気がする…」
臨床現場で、患者さんのこんな不安な言葉に、どう応えればいいか悩んだ経験はありませんか?
例えば、術後3ヶ月経っても膝の痛みが続く患者さんや、画像所見に明らかな異常がないのに腰痛が長引いている患者さん。これらに対し、「痛みの種類」を理解せずにアプローチを進めると、的確な説明も介入方針も立てにくくなってしまいます。
疼痛の分類を学ぶことは、「痛みのメカニズムを整理するための羅針盤(コンパス)」を手に入れるようなものです。正しいコンパスがあれば、私たちは臨床推論の航路に迷うことなく、自信を持って患者さんをゴールへ導くことができます。
- IASPによる最新の「痛み」の定義
- 3つの主要な疼痛分類(侵害受容性・神経障害性・痛覚変調性)の特徴
- 臨床で痛みの種類を推論するための思考ステップ
- 分類に応じた具体的なアプローチの選択肢
背景:なぜ、痛みの「分類」が必要なのか?
従来、痛みは単純に「組織損傷のシグナル」として理解されてきました。しかし、IASP(国際疼痛学会)は2020年に痛みの定義を大きくアップデートしました。
「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」
IASP Announces Revised Definition of Pain (2020)
この定義で、私たちセラピストが絶対に押さえておくべき重要なポイントは2つです。
- 痛みは常に主観的で個人的な体験であること
- 痛みは生物学的な要因だけでなく、心理的・社会的要因によっても強く影響を受けること
つまり、同じケガをしても、その人が置かれた状況や心理状態によって痛みの感じ方は全く異なるのです。だからこそ、痛みを多角的に捉えるための「分類」という指針が必要不可欠となります。
臨床で必須!3つの神経メカニズム的分類
痛みは様々な切り口で分類されますが、臨床で最も重要なのが、その発生メカニズムによる分類です。ここでは、時間的な分類(急性・慢性)も踏まえつつ、3つの主要な分類を解説します。
① 侵害受容性疼痛 (Nociceptive Pain)
原因:組織の損傷や炎症によって、侵害受容器(痛みセンサー)が興奮することで生じる痛み。
特徴:「ズキズキ」「ジンジン」といった痛み。原因部位と痛む場所が一致し、圧痛や特定の動作で痛みが再現されやすい。
臨床例:足関節捻挫、骨折、変形性関節症、手術後の創部痛など。
これは最も古典的で分かりやすい痛みです。身体の危険を知らせる「警告信号」としての役割を持っています。
② 神経障害性疼痛 (Neuropathic Pain)
原因:末梢神経や中枢神経(脊髄・脳)そのものが損傷されたり、機能異常を起こしたりすることで生じる痛み。
特徴:「ビリビリ」「電気が走る」「焼けるような」と表現されることが多い。しびれや感覚の鈍さを伴うこともある。
臨床例:坐骨神経痛、手根管症候群、糖尿病性ニューロパチー、帯状疱疹後神経痛など。
この痛みは、警告信号が故障し、神経系自体が痛みの発生源になってしまっている状態です。
③ 痛覚変調性疼痛 (Nociplastic Pain)
原因:明らかな組織損傷や神経障害がないにも関わらず、中枢神経系(脳・脊髄)の痛みの処理プロセス(痛覚伝達系の可塑的変化)に異常が生じることで起こる痛み。
特徴:痛みが広範囲に及んだり、日によって痛む場所が変わったりする。天候やストレスなど心理社会的因子の影響を受けやすい。疲労感、睡眠障害、感覚過敏などを伴うことも多い。
臨床例:線維筋痛症、非特異的慢性腰痛、過敏性腸症候群、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など。
いわば「痛みの警報装置が過敏になりすぎている」状態です。慢性疼痛の多くのケースで、この要因が関わっていると考えられています。
【注意】臨床では複数の分類が混在する
実際の患者さんでは、これらの分類が複雑に重なり合っていることがほとんどです。例えば、変形性膝関節症の患者さんでは、関節の炎症による「侵害受容性疼痛」に加え、痛みが長期化することで中枢が過敏になる「痛覚変調性疼痛」が合併しているケースが多く見られます。
臨床応用:評価から介入までの2ステップ
では、この分類を臨床でどう使えばいいのでしょうか?ここでは、診断ではなく、あくまで介入方針を立てるための「スクリーニング」としての思考プロセスを2つのステップで解説します。
ステップ1:どの痛みが優位か?分類を推論する
問診や身体評価から、どの痛みの要素が最も強く関わっているかを推論します。
- 痛む場所は解剖学的に説明できるか?
→ YESなら、侵害受容性疼痛の関与が大きい。 - 「ビリビリ」「焼けるような」痛みやしびれはあるか?
→ YESなら、神経障害性疼痛の関与を疑う。 - 痛みは広範囲か?日によって場所や強さが変わるか?ストレスで悪化するか?
→ YESなら、痛覚変調性疼痛の関与が大きい。
ステップ2:推論に基づき、介入の優先順位を決める
どの痛みが優位かによって、アプローチの重点が変わります。
- 侵害受容性疼痛が優位な場合:
組織修復の支援が中心。物理療法や、組織の治癒を妨げない範囲での運動療法、患者教育が有効です。急性期から慢性化させないための関わりが重要になります。 - 神経障害性疼痛が優位な場合:
薬物療法が有効な場合が多く、医師との連携が不可欠です。リハビリでは、神経の滑走を促す手技や、感覚入力の正常化を目指す感覚再教育などが選択肢となります。 - 痛覚変調性疼痛が優位な場合:
最も重要なのは、患者教育(Pain Science Education: PSE)です。「痛み=組織の損傷ではない」ことを伝え、痛みに対する恐怖や誤解を解くことが第一歩。その上で、段階的に活動量を上げていくアプローチ(Graded Exposure)などが鍵となります。
まとめ:疼痛分類は、臨床推論の「道しるべ」
疼痛の分類を理解することは、私たちの臨床に3つの大きなメリットをもたらします。
- 説明の枠組みになる:患者さんに「なぜ痛みが続くのか」を分かりやすく説明でき、納得感と安心感を与えられます。
- 介入方針が整理できる:組織にアプローチすべきか、神経系にアプローチすべきか、あるいは中枢の過敏性にアプローチすべきか、介入の優先順位が明確になります。
- 慢性化を予防できる:急性期から痛みの種類を意識することで、痛覚変調性疼痛への移行を防ぐための適切な予防策を講じることができます。
痛みは単なる感覚ではなく、その人の解釈や感情、社会的背景が複雑に絡み合った「体験」です。
この分類を“絶対的な診断名”としてではなく、患者さんを深く理解するための“臨床推論の道しるべ”として活用することが、リハビリの質を高めるための第一歩となるでしょう。
さらに深く学び、実践的なスキルを身につけたい方へ
この記事で解説した「BPSモデルに基づく痛みの臨床思考」を、もっと体系的に、実践的に学びませんか?
明日からの臨床が劇的に変わる、3日間の集中講座をご用意しています。