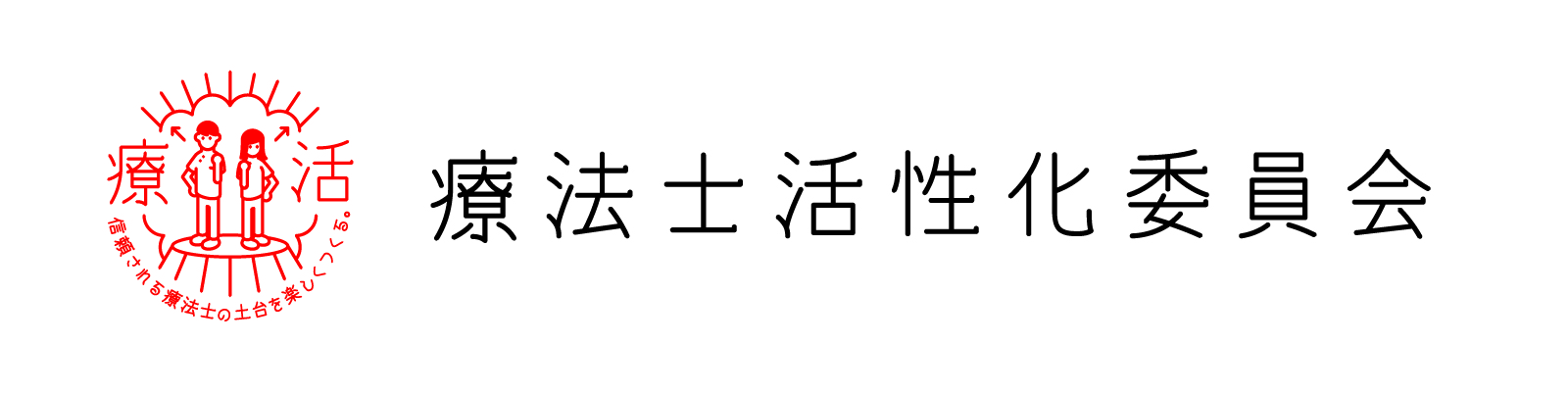この記事の要点(30秒で読めます)
- 尖足は可動域制限(短縮・拘縮)だけでなく、「運動選択の偏り」も大きく関与している。
- リハビリ以外の「23時間の空白」における環境(股関節・膝関節の条件)が、翌日の足部状態を左右する。
- 介入の本質は、手技による矯正に加え、背屈が自然に選択されやすい環境を再構成することにある。
【イントロダクション:リハビリ現場の葛藤】
若手:「先輩、担当している脳卒中症例なんですが、尖足が日に日に強くなっている気がします。リハの時間には持続伸張やモビライゼーションで背屈0度付近までアライメントを整えられているのに、翌朝になると元に戻っていて……。正直、何をやっても積み上がっていかない感じがしてしまって。」
先輩:「いわゆる『23時間の空白』だね。僕らが直接触れている40〜60分は、1日の中ではほんの一部にすぎない。特に脳卒中や脊髄損傷の症例では、リハ以外の時間にどんな肢位や使われ方をしているかで、次の介入時のスタートラインがほぼ決まってしまう。」
若手:「でも、病棟スタッフに専門的なストレッチや装具管理までお願いするのは、現実的には難しいですよね。血圧が不安定な時期だと、積極的に動かすこともできませんし。結局、ポジショニングくらいしか手がなくて……。それで本当に意味があるのか、正直迷っています。」
先輩:「その迷いはもっともだと思うよ。ただね、ここで考えたいのは『何かを強く矯正すること』じゃない。尖足に向かう使われ方が、24時間の中で選ばれ続けていないか、そこなんだ。」
若手:「使われ方、ですか?」
先輩:「そう。病棟での過ごし方は、治療の“おまけ”じゃない。配置や肢位を少し変えるだけでも、下肢がどの方向へ使われやすいかという条件は変えられる。手技として動かす介入を病棟に求めるのではなく、運動の選択が偏らない環境を整える。それも、れっきとした治療の一部なんだ。」
若手:「環境を整えるだけで、あの尖足の流れを変えられるんでしょうか。」
先輩:「少なくとも、尖足に向かう条件をそのまま放置しないことはできる。今日はその考え方を整理してみよう。」
こんにちは、理学療法士の土田です。上記の若手PTの疑問は、私自身も臨床の中で繰り返し感じていたものです。
リハビリで得られた効果をどうすれば打ち消さずに済むのか。
本稿ではこの問いを、運動学的視点から整理していきます。
1. 尖足の本質:可動域制限「だけ」ではない
尖足は、臨床的には足関節底屈位の固定として観察されます。もちろん、長期的な不動による軟部組織の短縮や拘縮といった「構造的な可動域制限」は無視できない要素です。
しかし、運動学的に捉え直すと、尖足は単なる可動域制限だけではなく、距腿関節において底屈が選択され続ける状態(運動制御の問題)が混在していると考える方が妥当です。
2. 運動連鎖における各関節の役割
では、足部以外の下肢関節はどのように尖足(底屈選択)に関与しているのでしょうか。
■股関節:方向性を決める関節
股関節は、下肢全体の回旋方向や緊張配分の基調を決定します。
股関節の肢位は、下肢が身体を支持する状態として扱われるか否かという前提条件を形成し、その影響は末端である足関節に集約されます。股関節は尖足を直接生じさせるわけではありませんが、尖足が選択されやすい方向性を下肢全体に与える関節といえます。
■膝関節:支持条件を切り替える関節
膝関節は、構造的に「身体を支持する状態」を左右する関節です。
- 膝関節を伸展位で放置する: 「今は踏ん張るときだ(支持期)」というサインを送り続けることになり、(特に脳卒中後の伸展パターンが出現しやすいケースでは)結果として底屈方向の運動選択が強まりやすくなります。
- 膝関節を軽度屈曲位に保つ: 下肢の役割を「支持は不要」と変調させ、足関節における底屈選択を弱めることに繋がります。
これは単なる筋長の問題だけでなく、下肢全体の運動方向を切り替える運動学的操作としても重要です。
■足関節(距腿関節):最終出力点としての構造的特性
足関節、とくに距腿関節は、これら上位関節の条件をすべて受け取る最終出力点です。
距骨滑車の形状により、距腿関節は背屈位付近で骨性適合性が高く、底屈位ではその制約が弱くなります。足部が底屈位で保持されると、距腿関節は構造的に安定しやすい角度域(骨性適合性が高い角度)から外れ、関節位置の保持は骨や靱帯ではなく、筋活動や環境条件に依存しやすくなります。
3. 内反(回外)が生じる力学的必然性
この状態では、距腿関節が底屈位で保持されることにより構造的制約が弱まり、後足部は回外方向への自由度が高くなります。
脳卒中片麻痺などでは、後脛骨筋をはじめとする回外筋群の過活動(痙縮)が内反の主因となることは多々あります。しかし、「それだけ」が原因ではないという視点も重要です。
ベッド上のような非荷重かつ底屈位で保持される環境では、これらの条件が成立しにくく、回内を維持する筋活動が選択されにくい状況にあります。その結果として、痙縮の影響に加え、環境的にも回外寄りの配置へ移行しやすいのです。
4. 結論:環境再構成としての介入
ここで重要なのは、尖足や内反を「筋緊張や短縮の結果」とだけで片付けないことです。
運動学的にみれば、尖足とは「誤った運動」というだけでなく、その環境条件下で最も選択されやすい運動が、結果として繰り返されている状態(そして、その反復により二次的に拘縮が進む状態)とも捉えられます。
したがって尖足への介入とは、距腿関節の可動域を一時的に修正することだけではなく、股関節・膝関節を含めた下肢全体の運動学的条件を再構成し、距腿関節において背屈が再び選択可能となる状況を整えることだといえます。
尖足は足関節に現れますが、その成立は下肢全体の運動連鎖によって規定されている現象なのです。
まとめ
- 尖足は距腿関節に現れるが、成立は下肢全体の運動学的条件によっても左右される
- 尖足は可動域制限「だけ」ではなく、距腿関節における運動選択の偏りが混在している
- 内反は回外筋の過活動に加え、環境的に回内筋群が選択されにくいことも影響する
歩行分析の「なんとなく」を1日で卒業! 実技で学ぶ評価と治療のつながりと臨床推論
参考文献
・Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. SLACK; 2010.
・Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System. Elsevier; 2017.
・Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. Wiley; 2009.
・Basmajian JV, De Luca CJ. Muscles Alive. Williams & Wilkins; 1985.
・Kandel ER, et al. Principles of Neural Science. McGraw-Hill; 2021.