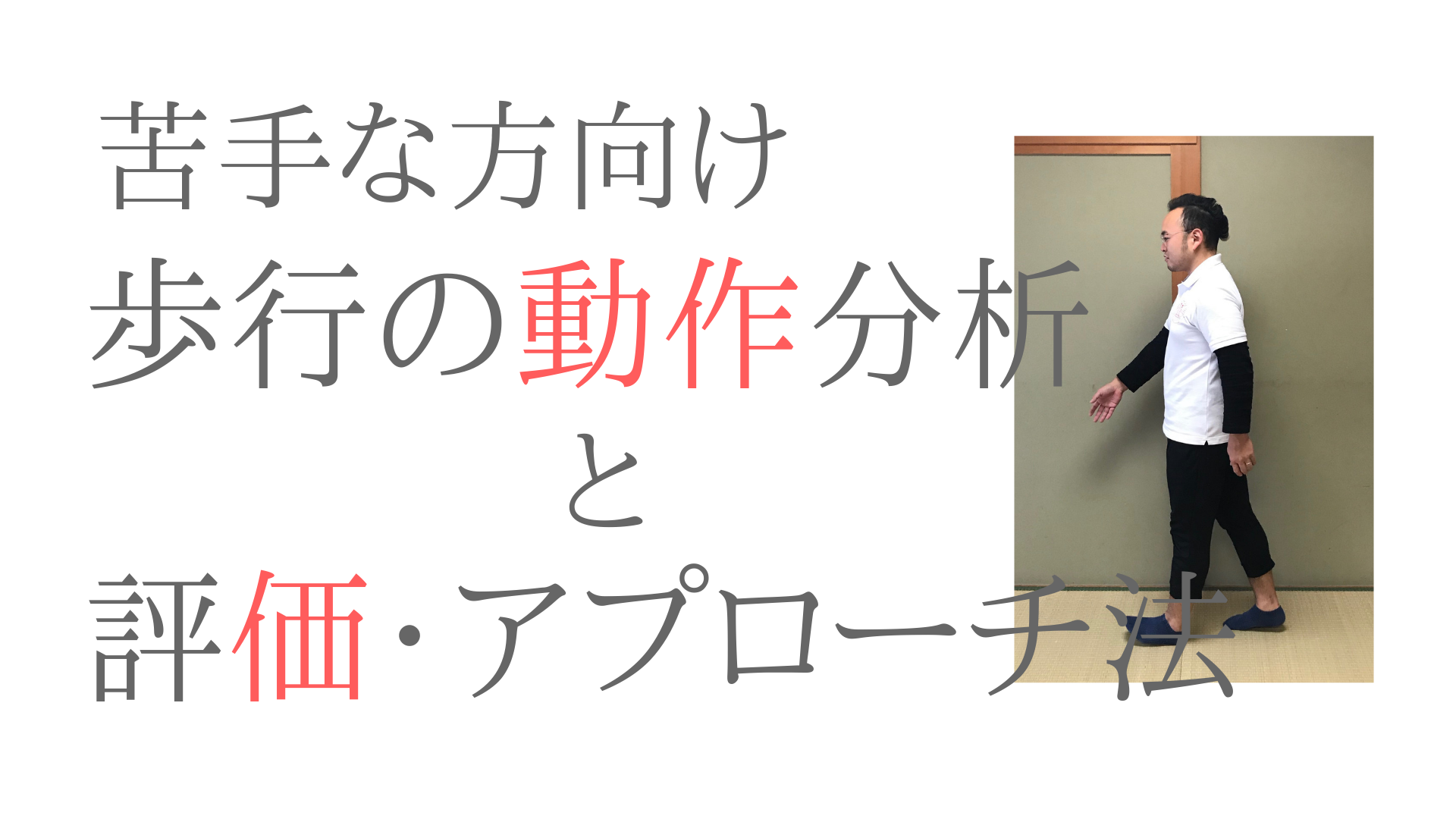こんにちは、臨床実習での歩行分析のが「歩けてます」の一行だった療法士活性化委員会委員長理学療法士の大塚です!

動作分析って療法士に必要な技術ですが正直どこからみたいいかわからなくないですか?僕も全くわからず、バイザーの先生に聞いたら「まず全体像を捉えるんだ」と言われ、全体像を捉えた結果が「歩けてます」でした。
今回の記事ではどこからみたらいいかわからない方向けに見るポイントを絞ってお伝えします。
歩くってどういうこと?
体を目的地まで移動する手段の一つとここでは定義しましょう。体というと大きくなるので重心を目的地まで移動するとよりいいかもしれません。
そうなると重心が目的の方向に移動するのが効率の良い歩行になります。
歩行で見るポイントは
重心が目的の方向に移動するのが歩行と定義したので、まず重心に一番近い股関節をポイントにみてみましょう。
重心が前方に移動するには股関節の伸展が必要になります。なので立脚期の特に中期〜後期に股関節の伸展が出ているかどうかをみてみましょう。
下肢のポイントは足部
重心が前方に移動するには下腿が前傾する必要があります。もちろん足関節の背屈も出る必要がありますが、ヒールコンタクトから立脚後期までそこまで大きく背屈は見られません。なので下腿がヒールコンタクトから立脚後期まで前傾していくかを見てみましょう。
例えば反跳膝の方はヒールコンタクトから立脚中期にかけて下腿が後方に倒れます。こうなると重心の移動は前方なのに下腿は後方に動くという効率の悪い歩行となります。
上肢は?
上肢の動きのポイントはズバリ肩甲骨。肩甲骨が前方に移動するかどうかをみてみましょう。
例えば片麻痺の方で肩甲骨を引き込んでいる方などは肩甲骨が後方に惹かれているため効率の悪い歩行となります。
まず最初はこの3つのポイントをみてみましょう。この肩甲骨、股関節、下腿の動きは割と大きく動くポイントですので観察も他に比べたら容易になります。もちろん他にもたくさんの見るポイントがありますが、動きが少なかったり、見るところが多すぎて結局どこも見れなくなってしまいます。
まずはポイントを3つに絞ってみましょう。
3つのポイントをみたら次は評価
それぞれ、股関節の伸展、下腿の前傾、肩甲骨の前方移動のポイントをみたと思います。それぞれが出来いなければ局所の評価をしてみましょう。
評価はシンプルに
- 股関節の伸展
- 足関節の背屈
- 肩甲骨の外転
の可動域、筋力を評価してみましょう。
問題点に対してアプローチ
股関節の伸展制限に対して
股関節の関節包内運動の問題
大腰筋の機能不全
大殿筋の機能不全
ハムストリングスの機能不全
足関節の背屈
近位脛腓関節の可動性
距腿関節の関節方内運動の問題
下腿三頭筋の機能不全
前脛骨筋の機能不全
肩甲骨の前方移動
胸椎の可動性
肩甲骨の可動性
前鋸筋の機能不全
などにアプローチしてみましょう。
機能的な改善ができたら運動療法として
- リーチ動作
- ステップ動作
などの練習をしてみましょう。
最後に歩行を再評価して効率の良い歩行になっていればオッケーです。
最後に
いかがでしたでしょうか?最初にどこからみていいかわからない時はこの3つのポイントから見ていくのがオススメです。
もちろんただ歩くだけでは意味がありません、料理をした、お墓まいりに行きたい、近所の公園に行きたい、趣味で公民館まで行きたいなどなど様々な目的があります。その目的のための歩行だということを忘れないようにしてください。もし機能改善の望めないケースで歩行が難しければ車椅子などの選択肢も必要です。
ぜひ患者様のHOPEを一緒に達成できる療法士になりましょう^^
記事の目次ページへ →
 この記事が「おもしろい!」「為になった!」と思ってくださった方は、ぜひ「シェア」や「いいね!」をお願いします!!
この記事が「おもしろい!」「為になった!」と思ってくださった方は、ぜひ「シェア」や「いいね!」をお願いします!!
今すぐ「いいね!」ボタンを押して「療法士のためのお役立ち情報」をチェック!
↓ ↓ ↓ ↓