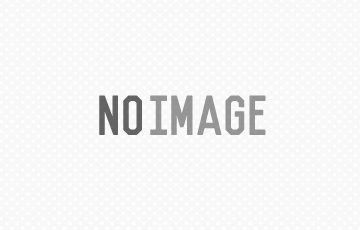こんにちは、理学療法士の内川です。
今回のテーマは、上肢の中でも「少しマイナーに感じられがちだけど、実はとっても重要!」な「烏口腕筋」です。
臨床現場でこんな疑問はありませんか?
- 「烏口腕筋って、結局どんな動きに関わってるの?」
- 「他の筋との違いや、臨床での評価・アプローチがあいまいかも…」
烏口腕筋は、小さく目立たない存在に思えるかもしれませんが、肩関節の安定性や動作の補助、そして肩甲骨と上腕骨をつなぐ重要な役割を担っており、臨床推論において見逃せない筋です。特に新人セラピストの方は、この機会にしっかり学んでいきましょう!
この記事では、烏口腕筋の解剖から臨床での評価・アプローチまで、具体的な内容を解説します。
この記事でわかること(目次)
1. 烏口腕筋の解剖と作用
まずは、烏口腕筋の基本的な解剖と作用を確認しましょう。

起始
肩甲骨の烏口突起
停止
上腕骨(内側面の中央あたり)
支配神経
筋皮神経(C5〜C7)
主な作用
- 肩関節の屈曲
- 肩関節の内転
- 肩関節の安定化(特に挙上初期に)
補足:体位・肢位による作用の違い
- 上肢下垂位では肩関節屈曲に働く
- 90°外転位では内転に働く
- 肩関節外転外旋位では上腕骨頭の安定化に働く
2. 烏口腕筋の評価・触診
臨床で烏口腕筋の状態を把握するための触診方法です。
烏口腕筋の触診方法
- 患者さんに仰臥位になってもらいます。
- 肩関節を外転90°・軽度外旋位、肘関節を最大屈曲位にします。(この肢位で烏口腕筋が触知しやすくなります)
- 三角筋前部線維の下方、上腕二頭筋短頭の内側を触知します。
- 患者さんに軽く水平内転方向に力を入れてもらい、烏口腕筋の収縮を確認します。
※触診時は上腕動脈や神経血管束に十分注意しましょう。

3. 烏口腕筋へのアプローチ(リリース)
烏口腕筋の機能改善に向けたアプローチ例です。
烏口腕筋のリリース方法
- 先述の触診で確認した部位(烏口腕筋)に軽く触れます。
- 患者さんが痛みのない範囲で、筋に対して優しく圧をかけます。
- そのままの状態で、患者さんにゆっくりと深呼吸を5回ほど繰り返してもらいます。
※強い圧迫や、神経血管束への刺激に注意してください。
4. 烏口腕筋の機能低下と臨床への影響
烏口腕筋の機能が低下すると、以下のような影響が考えられます。
- 肩関節屈曲、特に動き出しの不安定性につながることがあります。
- 上腕二頭筋短頭とともに肩関節の前方構造を支えているため、機能低下は肩前方の不安定感や違和感の原因となる可能性があります。
- 疼痛性収縮抑制(PIIS)などにより、インピンジメント症候群などの症例で筋活動が抑制されやすく、二次的な筋萎縮や筋力低下を招くリスクがあります。
5. 烏口腕筋 臨床ちょこっとメモ
臨床で役立つ、烏口腕筋に関する追加のポイントです。
- 肩関節の前方安定性を保つための「深層安定筋」の一つとして重要視されています。
- 上腕骨骨折後や肩関節の手術後リハビリテーションにおいて、烏口腕筋の機能回復は非常に重要となる場合があります。
- 烏口突起には、烏口腕筋の他に上腕二頭筋短頭、小胸筋が付着し、さらに烏口肩峰靭帯なども関係します。烏口突起周囲の解剖学的構造を統合的に理解することで、より精密な触診や効果的な治療につながります。
- 烏口腕筋を筋皮神経が貫通する解剖学的特徴があります。結帯動作など、烏口腕筋が伸張される肢位で、筋皮神経の絞扼による前腕外側のしびれや感覚異常が生じるケースも報告されており、鑑別診断で考慮に入れる必要があります。
6. まとめ|烏口腕筋の臨床的意義
この記事で解説した烏口腕筋の重要なポイントを3つにまとめます。
- 解剖と基本作用:烏口突起を起始とし、上腕骨に停止。筋皮神経支配で肩関節の屈曲・内転に働くほか、体位によっては上腕骨頭の安定化に寄与します。筋皮神経が貫通する特徴も重要です。
- 評価とアプローチ:仰臥位の特定肢位(肩外転90°・軽度外旋、肘最大屈曲)での触診が臨床評価の基本です。アプローチとしては、触診部位への痛みのない範囲でのリリースが有効な手段の一つです。
- 臨床的意義と機能障害:肩前方の深層安定筋として重要な役割を担います。機能低下は肩関節の不安定感や屈曲初期の動き出しの不安定性につながるほか、筋皮神経の絞扼による神経症状の原因となる可能性もあります。骨折や術後のリハビリでも機能回復が重要視されます。
この記事で烏口腕筋への理解は深まったでしょうか?
今回ご紹介したのは、あくまで烏口腕筋という筋単体に焦点を当てた内容です。実際の臨床では、烏口突起周囲には烏口腕筋だけでなく、上腕二頭筋短頭、小胸筋、さらには神経や血管など、様々な組織が複雑に関係しています。これらの組織が互いにどう影響し合っているのか、深層の解剖を立体的にイメージできているかが、正確な評価や効果的なアプローチには不可欠です。
もし、「周囲の筋肉や神経血管との位置関係をしっかり理解したい」「深層の解剖を自信を持って臨床に活かしたい」と感じているなら、ぜひ私たちの解剖セミナーで一緒に学びませんか?
解剖の知識は、セラピストとしての臨床能力を確実に向上させます。さらに深く学びたい方は、ぜひチェックしてみてください。