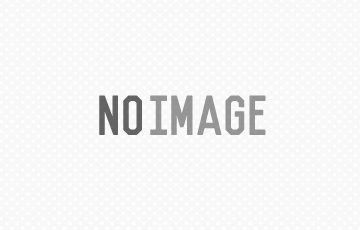理学療法士・作業療法士のみなさん、こんにちは。作業療法士の仲田です。今回は、リハビリテーションの核となるICFの「活動」について、評価の質を上げるための実践的な視点と記載方法を解説します。単に「できる・できない」で終わらせない、一歩踏み込んだ評価方法を身につけましょう。
この記事は、私が開催するZoomセミナー「OTしゃべり場」で、参加者の療法士さんから実際にいただいた質問への回答が元になっています。
「できる/できない」で終わらせない!活動評価の4つの視点
ADL動作などを評価する際、単に「自立」「介助」と書くだけでなく、以下の4つの視点を持つことで、評価の質が格段に上がります。
活動評価の4つの視点と記載例
- 1. 実行可能性(どのような条件下で可能か?)
例:「トイレ動作は病棟内の手すりがあれば自立。しかし自宅の段差があると介助が必要」 - 2. 補助具・代償手段(何を使って行っているか?)
例:「スプーン操作は右手で可能だが、左手での器の固定が困難なため、滑り止めマットを使用」 - 3. 時間・質・安全性(どのように行っているか?)
例:「更衣動作に標準の2倍の時間を要するが自立」「立位バランスに不安があり、移乗時に転倒リスクが高い」 - 4. 評価ツールとの連動(客観的な指標はどうか?)
例:「FIM食事項目は6点だが、むせ込みがみられ、STによる評価が必要」
分析が鍵!「なぜできないか」から目標設定へ繋げる
質の高い評価の次は、質の高い分析です。評価結果から「なぜその活動が困難なのか」という要因を分析し、具体的なリハビリ目標に繋げていきます。
「活動」を「参加」に繋げる作業療法の視点
私たち作業療法士は、単に動作ができるようにするだけではありません。その活動が、患者さんの意味のある生活、つまり「参加」にどう繋がるかを常に意識します。
まとめ:ICF「活動」評価で明日から使える3つのポイント
- 評価は「4つの視点」で具体的に記述する
「実行可能性」「補助具」「時間・質・安全性」「評価ツール」の視点で、誰が読んでも状態がわかるように書く。 - 「なぜできないか」を分析し、目標設定に繋げる
評価の裏にある要因(筋力、バランス、認知、心理など)を分析し、具体的なアプローチの根拠とする。 - 活動を「参加」への橋渡しとして捉える
単なる動作の獲得でなく、その人にとって「意味のある生活行為(参加)」にどう繋がるかを常に意識する。
臨床での評価・分析能力をさらに高めたい方へ
「評価の視点をもっと増やしたい」「根拠のあるアプローチができるようになりたい」
そんな想いを持つ療法士仲間と一緒に学びませんか?
療法士活性化委員会では、ICFの活用法やADLアプローチなど、臨床の質を上げるためのオンライン講座を多数開催しています。