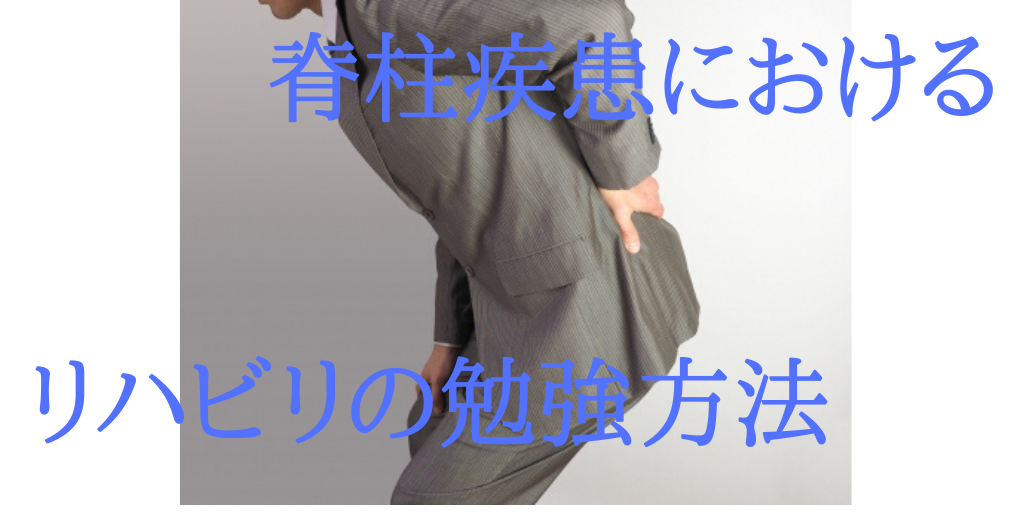みなさん、こんにちは!
整形外科クリニック勤務の林です。

皆さんは脊柱疾患の患者さん、利用者さんに対してリハビリはどのようにを行っていますか?
・脊柱圧迫骨折
・脊柱管狭窄症
・腰椎椎間板ヘルニア
などの症例を担当した時どのようなリハビリをしていいか悩みますよね。
僕もたくさん悩んで仕事が嫌になったことがありました。
今回は脊柱疾患に対してのリハビリ方法を療活のコンセプトを用いて
ご紹介したいと思います。
一緒に患者さん、利用者さんを良くしていきましょう!!
1、脊柱疾患のリスク管理
2、脊柱疾患の評価
3、脊柱疾患の介入
4、脊柱疾患のまとめ
1、脊柱疾患のリスク管理

脊柱疾患ののリハビリでは、
問診、画像データや血液検査などでたくさんの情報をみる必要があると思います。
正直、何をみていいか分からないですよね?
そんな時は何を「目的」にリハビリをしているか考えてみると自ずと答えはでてきます。
よく聞かれる「目的」は
・一人でトイレに行きたい
・起きれるようになりたい
・立つときに腰が痛まないようにしたい
などが挙げられます。
その「目的」を達成するために【悪くしない】ように注意する必要があります。
疾患別の注意点では
脊椎圧迫骨折→再骨折、偽関節、バキューム像
腰椎椎間板ヘルニア→屈み動作、CRP値
脊柱管狭窄症→間欠性跛行の有無、足背動脈の触知による鑑別
などがあります。
詳しい内容は療法士活性化委員会のコラムや自身で検索してみたくださいね。
2、脊柱疾患の評価

評価する項目は先ほど挙げた「目的」に対しての内容となっていきます。
例えば
「起立時に腰痛が出現し自力では立ち上がれず、トイレ動作に介助を要する」
この患者さん、利用者さんのためには
・環境確認(トイレ内の物品確認)
・動作観察(起立)
・姿勢観察(座位)
・スクリーニング(FRT)
・可動性、伸張性検査(Patrick,PLF,Trunk rotation,Thomas)
などを用いて環境面、機能低下している部分に検討をつけていきます。
ちなみに関節可動域検査(ROM-T)、筋力検査(MMT)は事前に評価しておくことで、
患者さん、利用者さんと体の現状を共有できるので実施すると尚いいですね。
3、脊柱疾患の介入

介入は先ほどの評価を参考に
仙腸関節、腰椎、多裂筋、下位肋椎関節、胸椎、大腰筋、股関節
などが徒手で介入し状態を改善が期待できる部位となってきます。
徒手で介入して後は運動療法にて
体幹の可動性、安定性を引き出すexが求められています。
ある程度動きが改善してきたら、実際のトイレ等の生活場面のリハビリを行うと
スムーズに練習もできますので試してみてください。
3、脊柱疾患のまとめ

腰痛の原因のまとめは
1、リスク管理
2、評価
3、介入
になります。
ただ忘れてほしくないのは
患者さん、利用者さんの動作や日常生活の改善です。
疼痛の評価は大切なことですが、
そこを忘れてしまうと何のための評価・介入か分からなくなってしまいます。
私もついつい疼痛だけ追い求めてしまう傾向があるので注意しています。
皆さんも一緒に勉強して患者さん、利用者さんを良くしていきましょうね。
一緒に勉強していきたい!という方はこちら
>>>【20分で変化を出す】脊柱疾患に対する評価とアプローチ<<<
療法士活性化委員会
認定インストラクター 林凌磨
記事の目次ページへ →
この記事が「おもしろい!」「為になった!」と思ってくださった方は、ぜひ「シェア」や「いいね!」をお願いします!!
今すぐ「いいね!」ボタンを押して「療法士のためのお役立ち情報」をチェック!
↓ ↓ ↓ ↓